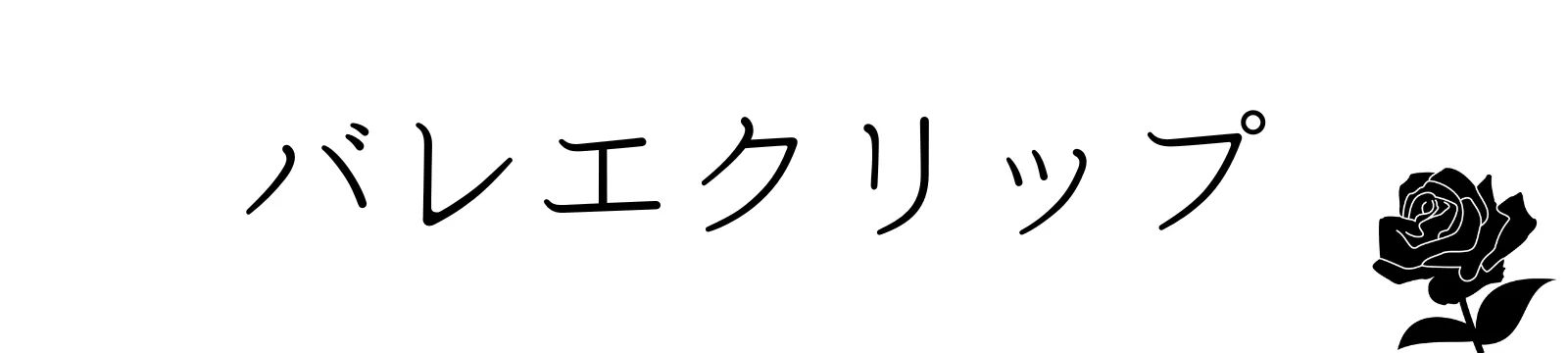- なんか必要以上に怒られている
- 八つ当たりじゃない?
- ちょっとしたことでイラつかれた
こんな経験したことはないですか?
普段はそんなことなくて、たまたまなら流せたりしますが、身近な人がずっとそんな状況だったらストレスがたまりますよね^^;
もしくは自分がそんな状態であることも。
それはそれでツライものです。
大事なものを失う前に、イライラを人にぶつける人の心理と対処法を知っておきましょう。
必要以上に怒る人の心理とは?
怒りが抑えられない人は大抵の場合、ストレスフルなことを抱えているを抱えています。
例えば、会社で上手くいっていない、成績かもしれないし、人間関係かもしれません。
または、仕事そのものが合わない。
こんな状況を抱えていて、且つ「仕方ない」と諦めている。
我慢を選択しているので、ストレスが溜まるわけです。
それを上手く解消しきれていない場合、自分の中にとどめておくことができず、
外へと出てくることがあります。
たまに、レストランやスーパーのレジで、店員さんに対して怒鳴っていたり、難癖付けたりしている人みませんか?
もちろん対応にイラっとすることは誰でもあると思いますが、それを怒鳴りつける人はあまりいません。
おそらく怒鳴るその人は、別の解消できない大きなストレスがあり、それを発散できる機会を得ただけなんです。
「怒りたくて、怒ることができる出来事が起こる」
まさしく、これなんです。
別の何かで不満を募らせてしまった。
でも、それを解消できずに飲み込む・・
そうして蓄積されたストレスが言いやすいと感じる状況&相手と出会った時に爆発します。
怒りをぶつけられる方が、家族やパートナー、同僚など身近な関係ということもあります。
怒鳴る場合もあれば、ネチネチとイライラをぶつけられたり、イヤな態度を取られたり・・身近なだけに頻発するのが問題です。
理不尽な怒りやイライラをぶつけられると何が起こる?
近い間柄の人から長期間または頻発して怒りやイライラをぶつけられている側に何が起こるかをお話します。
自分が悪いと思ってしまう
小言をずっと言われたり、ちょっとしたことで怒られることが多いと自分がいけなかったんだ、と思ってしまう人がいます。
本当は相手が自分の怒りを消化できず小さなことでも責めてくるだけなので、被害者なのですが。
だけど、人って不思議なもので、継続的に言われ続けると「そうなのかも」って刷り込まれます。
近くに「そんなことないよ」と否定してくれる人がいるといいんですけどね・・
こんな状況が続くと、元気がなくなって、気力が失われます。
自覚があるかもしれませんが、相手と一緒にいることがもう苦痛。。
自分を抑え込む癖ができる
言い返すことができる人で、相手と口論してもいいと思っている人は自分を抑え込む癖はできにくいです。
けど、相手に何か言うとめんどう、自分が我慢すればいい、どうせ起こるんだから・・という選択をすると我慢がクセになっていきます。
距離の取れる相手であれば、その方法でも問題ないです。
我慢が一時的なので何かでストレス発散すればいい。
けど、家族だとどうでしょうか?
我慢を重ね続けるでしょう。
その結果、自分のしたいこと、ほしいもの、夢・理想、などが考えられなくなります。
思い当たる人は試しに紙に100個望みを書き出してみてください。
あまりでてこないのではないでしょうか?
「望み」は原動力であり、道しるべ。
これを失ってしまうと今のこの状態が続きます。
もしくは悪化しちゃうんですねよ。。
必要以上に気を使う人になる
怒られるのは誰だって気持ちよくない。
なので、怒りやイライラをもらわないよう怒る人のご機嫌を伺うようになります。
そして必要以上に気を使うようになり、これが油を注ぐことも。
恐れられている、気を使わせている、と相手は思うので、余計にイラっとするのです。(理不尽ですよね)
問題はこの人に気を使いすぎる癖、他人にも出ちゃうことが。。
気の使い過ぎは、卑屈な印象を与えてしまい「気を使っているのに好かれない」といったことが起きるんです。
最悪なのは、そんな状態で別の怒りを消化しきれない人に出会ってしまったとき。
気を使ってくるから「言いやすい人」と判断され、必要以上に下手に出るので、イライラを刺激してしまい、攻撃を受けてしまう・・
これが、人を引き寄せちゃったケース。。
反論する人(自分を守る人)にはこれが起きないのです。
体調に異変がでてくる
心と体は繋がっていますよね。
例えば、緊張して体が思うように動かないとか、声が裏返ったり、汗かいたり・・ストレスを溜めすぎると体の不調として現れます。
痒みがでたり、胃が痛くなったり・・ストレス性〇〇といった病名も聞いたことあると思います。
病気とまではいかなくても、眠れない、食欲がない、食べすぎちゃうなどこれまでと違うことが起きることも。
そんな変化に敏感になってください。体ってとても優しくて、ストレスがあるよって信号を出してくれているんです。
対処法
一番、大事にしてほしいのは、「自分のことをちゃんと守る」です。
残念ながら怒りをぶつける相手はそう簡単に変わりません。
本人自身に気付きが起きる必要があるから。
なので、「自分を大事にするという決意」を持ってほしい。
ほんとね、思っている以上に自分を大事にしていないんです。
もしくは自分をおろそかにしていることに気づいていません。
とにかく最初は超積極的にリフレッシュ
あなたはとても頑張りました。
なので、溜めまくったストレスを一時的でいいのでリリースしましょう。
五感に着目するといいかもです。
人によってリラックスできるものが異なります。
視覚:映画や風景など
聴覚:音楽や自然の音
嗅覚:アロマや空気のきれないところ
味覚:食べ物
触覚:肌触りの良い布・マッサージ
少しの時間でもいいので、ひとりになってカフェや映画館、公園の散歩、マッサージなどでリラックスタイムを作ってください。
できれば、意思をもって、意図的に日常に差し込むこと。

ノートに思うこと全てを出す
ブレインダンプというものがあります。
頭の中に浮かぶ思考を全て紙に書き出すのです。
人には見せないので、どんな暴言も恥ずかしいことも不満や不安、望みもすべてノートなどに書き出します。
不思議ですが、書くだけで心が落ち着くんですよ。
思考は頭の中だけで留めておくと、とりとめもなく広がりやすい性質があります。
書き出すことで脳が整理されすっきりすることができます。
これはできれば、何回かやってほしいです。
誰かに自分の心のすべてを聞いてもらうかのように落ち着くと感じるまでやってみてください。
感情は溜めると腐ります!
落ち着いたら本当はどうしたいか考える
まずは自分に安心を与えられることを体感して、思うことを外に出します。
そうして、落ち着いてきたら、本当はどうなりたいか考えます。
それもノートに書いてみるとよいです。
一度きりではなくて、何度でも。
リフレッシュを覚えたことで、ストレスを発散しつつ、現状維持を続ける選択もありますが、時間は人生そのもの。
どう生きたいかは、どんな気持ちの時間を多く過ごしたいかとも言えます。
望むものがクリアになると、叶うわけないという思いも出てくるかもしれません。
けど、1mmだけ変化する勇気があればいいんです。バンジーする必要はないです。
心地の良い時間を5分だけでも作る、それは散歩でもいいし瞑想でもいいんです。
いつもと同じ流れに小石を投げる、そして少しだけ流れが変わる・・
これを意識的に繰り返しましょう^^
望まない人生から逃げる
小さな行動でも気力が必要で動きにくくなった状態になってしまった人もいます。
そんなときは、ココロに効く簡単なストレッチを取り入れてみてください。たった10秒で心はほぐれます。こちらの本では、辛いとき、うんざりした時、不安な時など状態に合わせたひとつのポーズが心に沁みる解説付きで紹介しています。
たった10秒で心をほどく 逃げヨガ
自分が怒りをぶつける側になったら
これは、起こりえることです。
自分のストレスやネガティブな感情を押し込む癖がある場合、怒りをぶつける側になることもあります。
激しく感情がでることもあれば、イライラの頻度が増して、言いやすい人にぶつけてしまうことも。
そして、後から後悔・・謝ることができるといいのですが、大抵の場合はそうできないでしょう。
これが続くと本当に大切な人を失います。
友人や仲間、パートナー、家族一緒に暮らしていても、相手の心は離れてしまい別離を望むこともあります。
あるいは、相手が心を病んでしまったり・・
そんな後悔・絶望は味わいたくないですよね?
そうならいために習慣にしたいのが、「内観」です。
自分は何に不満・不安でどうしたいんだろう。
何が辛いんだろう、何から逃げたい?どうしてそう思うの?自分の感情・気持ちを知るということです。
辛いを、放置しないこと。
今すぐ何かを変えようとしなくていいから、まずはただ知るだけでいいです。見ないふりしない。
私はストレスを感じるようなことがなくても頻繁にそんな時間を取ります。
専用のノートに思ったことを書き出す、これをクセにしています。
不安とか怒りがでてきたときは、ノートに思いのたけを全部書いています。
絶対に人に見せられないです 笑
でもそうすることで、気持ちが落ち着くことを体感。
書き続けているうちに、事実と想像(妄想)の切り分けができて、楽になることもよくあります。
自分の中で消化するので、他人を傷つける行動にはでにくいです。
ストレス解消と内観、これを習慣にしてみてください。
おわりに
内観する習慣は、メンタルの安定をもたらすだけではなく、理想や望みを叶えるツールにもなりえます。
ただ、ストレスが強い場合は、まずはメンタルを整えることからスタート。
マイナスからいきなり100を目指さない。まずは、0(フラット)を目指してみてください。
ホッとする時間が増える、これだけで人生は変わります。
ほんの小さなスタートでかまいません。1mmだけ変えてみる、にチャレンジしてみてくださいね。