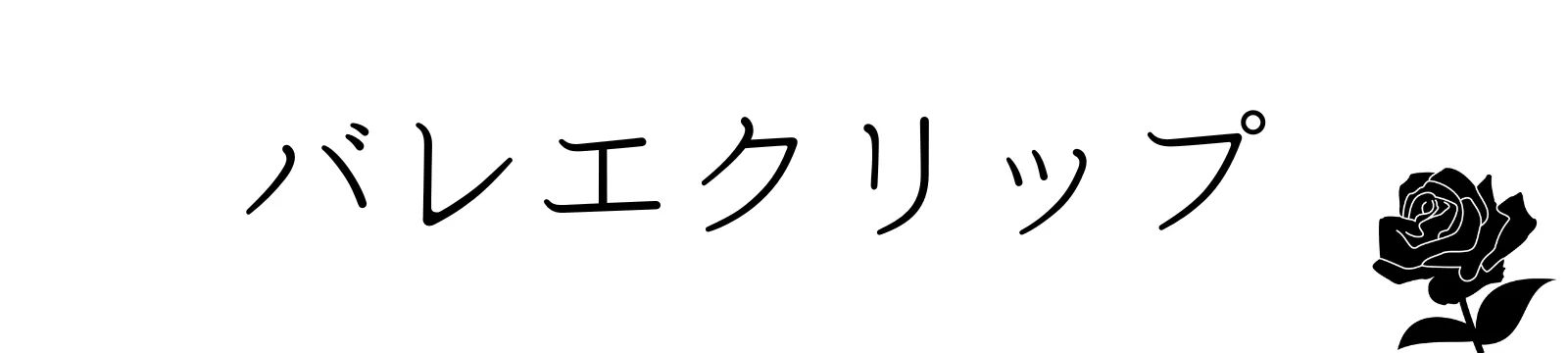バレエは子供の頃からしてないと見栄え良く踊れない、というイメージないでしょうか?
だけど大人から始めても上手くなりたい!と思うし、実際に上手な大人バレリーナはいますよね。
小さい頃にしていた復活組とかではなく、40代からスタートした方でも上手な方もいます。
大人も子供も関係ないと思いますが、同じ年数習っていても上達や習得には差があります。
これはバレエに限ったことではないですが、上達する人というのは確実にいるものです。
では、上達する人はなぜ上達するんでしょうか?
今日は上達する人の特徴のお話です。
バレエが上手な大人バレリーナに共通するもの
ポイントはいろいろあると思いますが、一番は・・
観察力。
上達が早い人はここが優れていると感じます。
観察力がある人の特徴のひとつは、人の変化にも気付きやすく、具体的に話すことができます。
ピラティスを始めて3か月、その効果がバレエに表れてきたようで、最近先生に身体が激変したって
(痩せたとかではない)と言われました。
変化したといっても、何回転も回れるワケでもなければ、脚が上がるようになったとかでもなく、
基礎的なカラダのこと。
その先生は生徒の身体的特徴を細かく見て、注意もひとりひとり異なります。
なので、私の体の変化に気付いたことに納得感はありました。
けど、別のスタジオのバレエ友達から「身体変わったよね!何したの?ピルエットがとても安定している」
と質問されたんです。
質問してきたのは、40代半ばからバレエを始めたという上手な大人バレリーナさんだったのですが、
これはちょっとびっくり!
気付くんだって^^;
考えてみれば、彼女と話していると先生や他の人の素敵だと思ったところ、自分ができないところ思うことが
すごく具体的なんです。
上手な人を見ても、「上手だよね~」では終わらずに、ルルベがポアントで立っているかのよう、パッセが開いていて美しい回転だったなど良かった点を具体的に誉めてます。
また、自分はルルベした時に母指球に体重が上手く乗らないんだよね、と自分自身の分析も具体的。
「バレエがよく見えている」人だなと。
なぜ観察力が高いと上達するのか

例えば、ピルエットをもっと美しく、たくさん回りたいと思っているとします。
でも漠然と回りたいなぁだと、なかなか道のりは長そうですよね^^;
どこを直すべきなのかが曖昧だからです。
ピルエットができない理由はたくさんあります。
一例を出します。
- 膝が伸びてない
- 顔がついてない
- パッセがインに入っている
- 脇(肘でも)が落ちている
- パッセが脚から離れている
- 引きあがってない、落ちている
聞き覚えのある注意かもしれません。
観察力が高い人たちは、その注意を視覚的にとらえて理解していると思います。
目指すべき姿と、できていない姿を頭の中で思い描けているのです。
現在地とゴールが明確なんですね。
「具体的に言語化できる」
これは観察力の賜物です。
できていないところが具体的になると行動に移しやすいものです。
先生に質問したり、動画でプロのを見て学んだり、ネットで調べたり・・
その知識でできていないところを想定し、身体への意識が高い状態で練習をする・・
上達するわけだなって思います(*^-^*)
「なんか回れないんだよね。バランス取れないんだよね」
と言っている方と
「パッセが外れてしまって、途中で踵が落ちてしまうんだよね」
と言う方・・
後者の方が自分の身体の観察力が高めです。
できない理由が具体的にわかっていて、想定できています。
だからそれを練習しますよね。
ピルエットの時だけではなくレッスン全体を通しながら。
具体的に直すべきところが分っている人は、改善されるにつれて上手くいくピルエットの再現性が高くなります。
上手くいく理由も失敗する理由もわかっているから。
一か八かのピルエットから脱出しています 笑
まとめますと、観察力を磨くことでの恩恵は
- 直すべきところがより具体的に見る
- 知識が増えてきて、レッスン中の身体への意識が高まる
- 再現性が高まる
観察力の高め方

では、どうやって観察力を高めていくか。
先生の見本を凝視するのもひとつですが、他の人を利用することです。
先生の見本と他の人はどう違うのかを観察してみるのです。
比べることで見えてくるものがあります。(踊っている自分を注視することは難しいので・・)
例えばですが、海外のお寿司好きな外国人が日本に来てお寿司(回転寿司でも)を食べると感激しているテレビとか見たことないでしょうか?
現地で美味しいと思っていたお寿司も、本場で食べるとはるかに美味しかった、みたいな出来事です。
比較対象ができたことで、なぜそれが美味しいのかわかるようになったりします。
魚の新鮮度やシャリの握り具合、具材の切り方など、比べて初めて気付くこと・・・
これと同じで先生と仲間を見比べて情報を得ましょう。
ただし、注意点が2つあります。
- 観察を批評(ジャッジ)にしないこと
周りの人を観察するのは、「観察して、直すべきところを得る」ことが目的であって、その人の踊りを批評(ジャッジ)するためではありません。 - あまり見すぎないこと
失礼だから、というより脳は見たものを無意識に覚えて記憶するそうなので、じっとみるなら先生のを見てくださいね。
観察眼はどんどん磨かれていきます。
最初は大きな違いしか見えないかもしれません。
けれど続けていくと、見る目が深化して、細かい部分に気付けるようになります。
グランバットマンを観察したとします。
最初は大きく動く動足に目が行くと思います。
どうやったらキレイに高く上がるかなぁと注視しますよね。
膝が伸びているなぁ、つま先がキレイに伸びている、から始まって、軸足側のボディが安定しているなぁ、
骨盤はそこまで激しく動かしているわけじゃないな・・
など細かい身体の使い方を見れるようになります。
こうなってくるとYouTubeのプロのレッスンも勉強できるところがいっぱいでてきます。
プロのなんて鑑賞用!ではなく、「どう身体を使っているんだろう?」という視点で見られると、
上達すると思いませんか?
大人バレエでも美しいバレエは手に入る

バレエはスポーツではなく、芸術だというのはよく耳にしますよね。
フィギュアスケートや新体操などのようにスポーツであれば、テクニックへの評価が高いので若いうちにピークがきます。
しかし、バレエは妙齢とも言えるダンサーの踊りも魅入ってしまうことがあります。
それは、柔軟性やジャンプ、回転などのテクニックだけが見せ場ではないからです。
バレエは「ラインを魅せる踊りだ」というを聞いたことはないでしょうか?
普通に立っているだけなのに、ちょっとした動きなのに品があって美しく見える・・
身体のライン、使い方を追求した結果なのだと思います。
大人から始めても身体の使い方を学び習得することは可能だと思います。
ぜひ観察力を見方にして、自分の身体への理解を深めていきたいですね。
コバナシ
先生がジュニアちゃんに対して、観察力が足りない!先生はそんな動きしてないよね?って言っているのを聞いたことがあります。
(先生は大人にはたいてい優しいから言わないけど 笑)全身を使って踊りますし、先生も身体全部のことを注意できるわけではない。
見て盗む、職人的な意識が必要なのかもしれません。